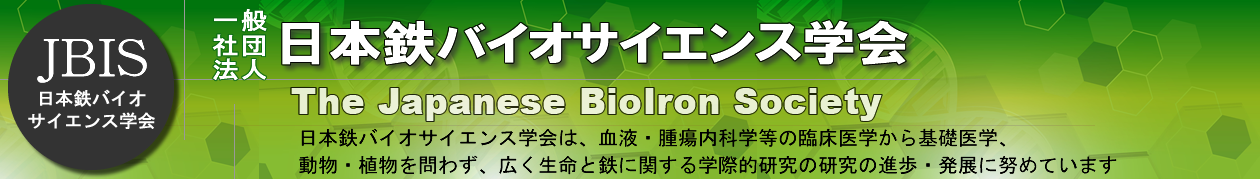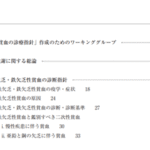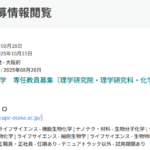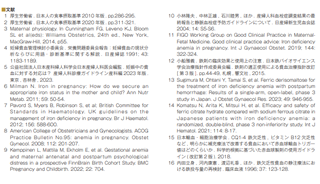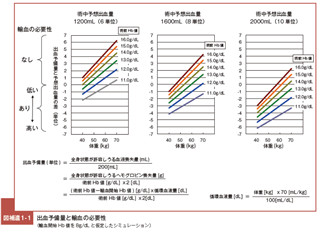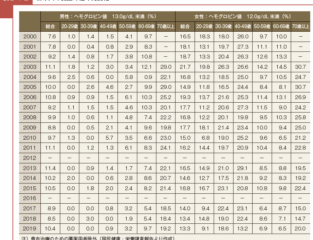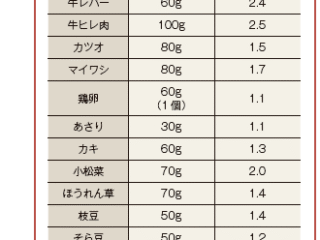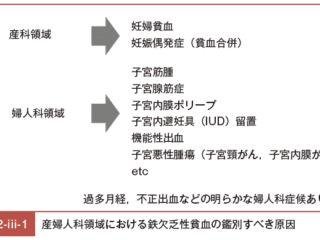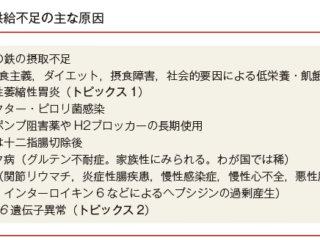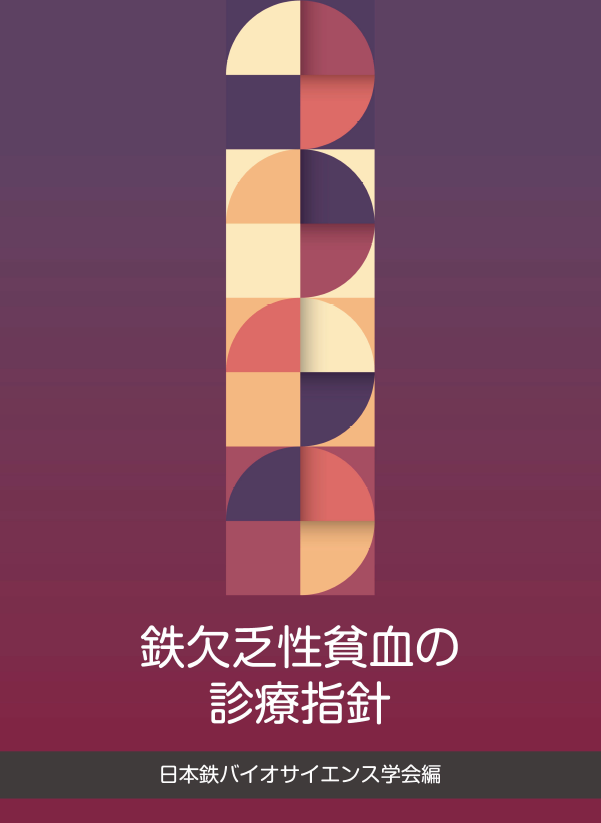
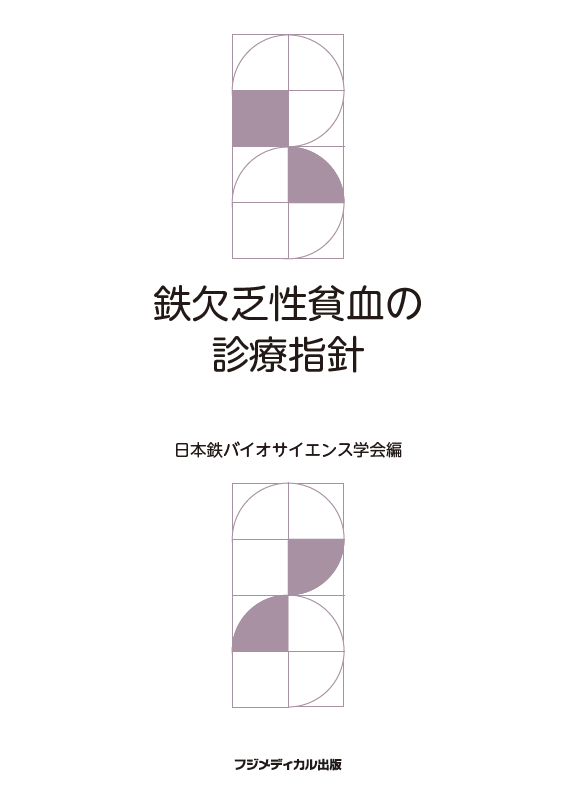
序文
これまで,日本鉄バイオサイエンス学会では,鉄欠乏・鉄欠乏性貧血の予防,治療に関する指針を示した『鉄剤の適正使用による貧血治療指針』の第 1 版を 2004 年に,第 2 版を 2009 年に,第 3 版を 2015年に出版してきた。しかしながら,最近では持続効果の高い静注鉄剤をはじめとした新たな鉄剤が普及しつつあり,鉄欠乏性貧血の診療に関する指針も改訂が必要な状況となっている。そこで,『鉄欠乏性貧血の診療指針【第1版】』を刊行し,鉄代謝に関する知識及び鉄欠乏性貧血に関する診療指針のアップデートを行うこととした。作成の際にはパブコメを実施して,その意見を参考にした。
本書は新たなタイトルでの刊行となるが,第 3 版を改訂する形をとっており,いわばこれまでの日本鉄バイオサイエンス学会の歩みを引き継いだものとなる。本学会の歴史,治療指針出版の意図,意義を確認する意味で,『鉄剤の適正使用による貧血治療指針』の高後裕先生による序文の一部を以下に引用させていただく。
一般社団法人日本鉄バイオサイエンス学会は,「生命と鉄」に関する研究の進歩,発展を目的として設立された学術団体である。本学会は,当初,わが国におけるコロイド鉄剤を開発した故妹尾左知丸教授(岡山大学病理学教室)が鉄欠乏性貧血の治療薬である静注鉄剤の普及と鉄欠乏性貧血の診断を含め,広く全国に声をかけ,「鉄代謝研究会」として始まったものである。当時は,放射性同位体を用いたフェロキネティクスの時代から,今も標準的に使用されている血清フェリチンの時代へ移行する節目の時であり,同時に鉄による細胞毒性や発がんに関する研究が飛躍的に進んだ時期でもある。
その後,本学会では,鉄欠乏性貧血,鉄過剰症などの臨床的課題から生体鉄に関する基礎研究に関し,内科学をはじめとした臨床医学,生化学,分子生物学,物理化学,生理学,微生物学などの医学領域,栄養学のみならず薬学,農獣医学など広い分野の課題に関するテーマを扱い,法人化され現在に至っている。
国際的にも,2007 年の第 2 回国際鉄バイオサイエンス学会総会を京都で日本学術会議と共催する母体となるとともに,国民への鉄と健康に関して公開講座をはじめとした啓蒙活動を積極的に進めてきた。
中でも鉄欠乏・鉄欠乏性貧血は,本学会が鉄代謝研究会として発足した当時から一貫して追求している最重要課題であり,開発国,開発途上国を問わず頻度の高い貧血であり,広く社会的な問題である。その予防については,国ごとに予防対策が講じられ,WHO や CDC が鉄欠乏予防のためのガイドラインを作成し,予防対策が継続されている。わが国においても,日本鉄バイオサイエンス学会が,2004 年に『鉄剤の適正使用による貧血治療指針(第 1 版)』を発行,2009 年には改訂第 2 版『鉄剤の適正使用による貧血治療指針』を出版した。
言うまでもなく,鉄欠乏性貧血は世界で最も頻度が高い疾患で,古くはギリシャ時代に鉄の服用により貧血が改善することが記載されている。さらに,食生活の変化,ダイエット志向など社会情勢の影響をうけ増加しつつあり,社会的にも重要である。血液学の黎明期においては,多くの医師,研究者がその研究に従事していたが,現在では「貧血は鉄剤を飲めば治る」という安易な考え方が広がり,鉄剤治療を支えるのに必要な系統的知識を得る機会が減っている昨今,この古典的な疾患に関する診断・治療の指針は重要である。さらに,世界的には新たな静注鉄剤も開発され,より安全で持続効果の高い鉄剤が急速に普及しつつある。
この序文で高後先生が指摘されている課題は,今もなお新しく,鉄欠乏性貧血の診療の重要性,そして本書の刊行の意義を改めて示すものである。
最後に,編集メンバーを代表し,多忙な中ご執筆いただいた先生方に御礼申し上げる。
2024 年 5 月
編集メンバー代表
張替 秀郎