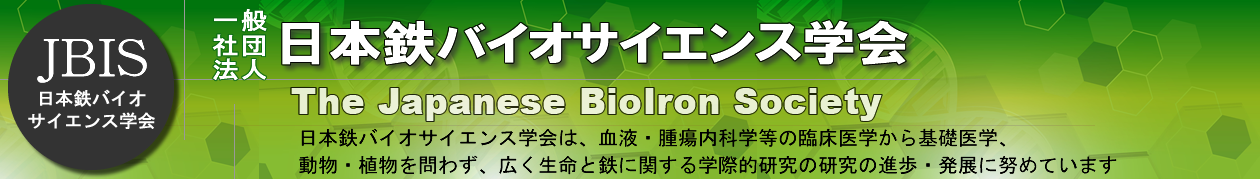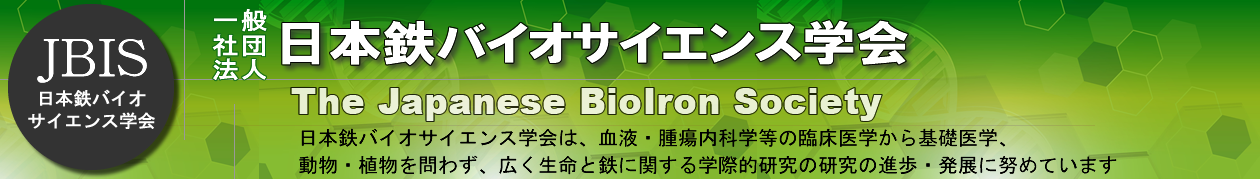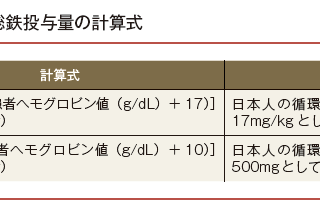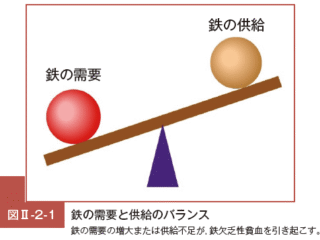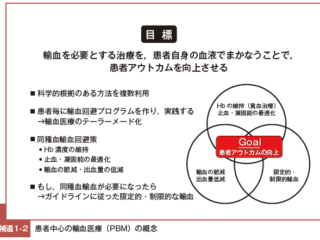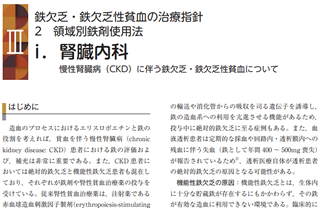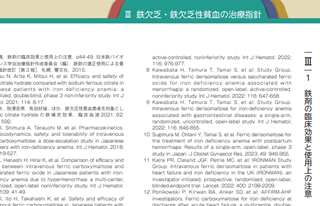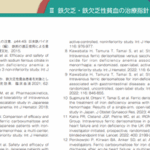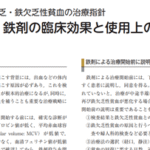ここ数年の間に登場した新規鉄剤は,いずれも本邦において複数の臨床試験が行われて有用性や安全性が確認されているので,一部を紹介する。クエン酸第二鉄水和物 ferric citrate hydrate(FC)FC は,元々は本邦で慢性腎臓病(chronic kidney disease: CKD)患者における高リン血症の治療に用いられていた薬剤である。 しかし,高リン血症患者に FC を投与することで貧血を改善することが見出され,その機序として FC の有効成分である三価鉄が消化管で還元されて吸収され,貧血を改善したと考察される。 その後,鉄欠乏性貧血患者対象の臨床試験で,従来広く使用されているクエン酸第一鉄製剤(sodium ferrous citrate: SF)を対照として,FC の有効性と安全性を検討する目的で第Ⅲ相臨床試験が実施されている2)。 FC 500mg(鉄として約 120mg を含有)/ 日投与群(FC-low 群:174 人),FC 1000mg/ 日投与群(FC-high 群:172 人),SF 100mg/ 日投与群(SF群:171 人)の 3 群で行われ,7 週間の経口鉄剤 投与後の平均ヘモグロビン変化量は,FC-low 群では 2.75g/dL,FC-high 群では 3.29g/dL であり,いずれも SF 群の 3.11g/dL に対して非劣性が証明された。 安全性(有害事象)に関して注目すべき点は,SF 群で最も頻度が高かった嘔気に関して,SF 群では 32.7% であったのに対して,FC- low 群で 15.5%,FC-high 群で 10.5% であり,FC投与 2 群で著明に低かったことである。 嘔吐に関しても,SF 群での 15.2% に対し,FC-low 群 5.2%, FC-high 群 1.2% であり,同様に SF 群に比べ FC群のほうが著明に低かった。 経口鉄剤の一番の弱点である嘔気・嘔吐の頻度が少ないことは,実臨床に大きく寄与できると考えられ,期待される。 鉄欠乏性貧血の治療では,ヘモグロビン値が回復した後も,貯蔵鉄が回復するまで鉄補充を継続することが推奨されるため,FC 500mg/ 日(FC- low 群:36 人)および FC 1000mg/ 日(FC-high 群: 37 人)を最長 24 週間投与した臨床試験も行われている3)。 各群の平均服薬期間は 119.2 日(FC-low群)および 114.4 日(FC-high 群)であり,服薬率は 97.3%(FC-low 群)および 92.7%(FC-high 群)と非常に高かった。 血清フェリチン値は,両群とも FC 投与開始後に確実に上昇しており,最終投与時の血清フェリチン値は 41.64 ± 19.10ng/mL(FC-low 群)および 50.81 ± 48.69ng/mL(FC-high群)であった。 なお,有害事象は 58.3%(FC-low群)および 67.6%(FC-high 群)に認められたものの,多くは軽度であり,FC 投与量に伴う違いは認められなかった。 本試験の結果から,FC は長期間にわたって安全かつ確実に鉄補充を行える薬剤と考えられ,この点からも今後が大きく期待される薬剤と言える。 カルボキシマルトース第二鉄 ferric carboxymaltose(FCM)FCM は,水和された酸化第二鉄とデキストラン非含有カルボキシマルトースの複合体である。 静脈中に投与されても,フリーな鉄が急激に血液中に遊離してこないとされる。 本邦では週に1 度, 1 回 500mg での投与が認められている。 従来使用可能な含糖酸化鉄の 1 日最大投与量が 120mgであるので,かなり多い鉄を 1 回で投与できることになり,静脈注射の回数が少なくても鉄が確実に補充できる利点がある。 総投与鉄量は,患者のヘモグロビン値と体重により添付文書の簡易早見表で定められている。 FCM は以前から海外では広く使用されていたが,日本人において有効かつ安全に使用できることを検証するため,臨床試験が行われた。 過多月経を伴う日本人鉄欠乏性貧血患者を対象に,含糖酸化鉄に対する FCM の非劣性を検証する目的で,国内第Ⅲ相試験(多施設共同無作為化非盲検並行群間比較試験)が行われた5)。 対象患者 238例は無作為に FCM 投与群 119 例と含糖酸化鉄投与群 119 例に割り付けられた。 背景疾患は,子宮筋腫が最も多く,それに続くのが子宮腺筋症であった。 FCM 群では 1 回投与量 500mg を緩徐に静注または点滴静注とし, 含糖酸化鉄群では 80mg もしくは 120mg を 2 分以上かけて緩徐に静注とし,患者のヘモグロビン値と体重から求めた総投与鉄量(1000mg もしくは 1500mg)に達するまで投与を続ける試験デザインで行われた。 その結果,ヘモグロビン最大変化量は,FCM 群では 3.90g/dL,含糖酸化鉄群では 4.05g/dL であり,非劣性が証明された。 Hb 値の平均値は両群共に投与開始 12 週時に最大となり,FCM 群 12.76g/dL,含糖酸化鉄群 12.99g/dL でほぼ同等であった。 血清フェリチン値の平均値は,FCM群では投与開始 2 週時に最大値359.30ng/mL,含糖酸化鉄群では投与開始 6 週時に最大値219.47ng/mL と動きに差が出た。 しかし,こうした FCM 投与による投与早期の一過性の血清フェリチン値高値は,その後徐々に低下して,最終的には含糖酸化鉄と同等に基準範囲内に落ち着いており,高値を示した時期にも特に有害と考えられる臨床症状は認めておらず,安全性には問題ないと判断された。 本試験における副作用は全体として,FCM 群 119 例中 45 例(37.8%), 含糖酸化鉄群 119 例中 39 例(32.8%)に認められた。 血中リン減少は各群共 20% 程度で最も頻度が高かった。 続いて消化管出血を対象として,国内第Ⅲ相試験(多施設共同非対照非盲検試験)が行われた6)。 消化管出血に起因する日本人鉄欠乏性貧血患者 39 例を対象とし,FCM は 1 回投与量として500mg を 1 週間以上の投与間隔で,投与前に決定した総鉄投与量(1000mg または 1500mg)に達するまで点滴静注を行った。 背景疾患は,クローン病,潰瘍性大腸炎,大腸憩室出血が全体の 8 割以上を占めていた。 結果としては,投与 12 週時までのヘモグロビン最大変化量の平均値は 3.31g/dL であり,良好なヘモグロビン改善効果を示した。 血清フェリチン値の平均は,投与開始 2 週後に 417.56ng/mLと最大値を示したが,その後は徐々に低下することが確認され,やはり安全性に問題はないものと判断された。 48.7% に副作用が認められ,血中リン減少 9 例(23.1%)が最も多かったが,重篤なものは認められなかった。 デルイソマルトース第二鉄 ferric derisomaltose(FDI)FDI は,酸化第二鉄と,免疫原性の低い低分子直鎖状オリゴ糖であるデルイソマルトースから成るマトリックス組成の複合体である。 体内に静脈内投与されても,血液中に鉄の遊離を起こしにくく,網内系細胞に取り込まれてから鉄が遊離され利用されるため,1 回に 1000mg(体重 50kg 未満の場合は 20mg/kg)まで投与可能な静注鉄剤である。 総投与鉄量は 2000mg(体重 50kg 未満の場合は 1000mg)まで可能であり,投与回数が少なく,1 〜 2 回の投与で確実に鉄が補えるという利点がある。 総投与鉄量は,患者のヘモグロビン値と体重により簡易早見表で定められている。 過多月経による日本人鉄欠乏性貧血患者 356 例を対象とした国内第Ⅲ相試験で は,FDI 群(n=237)と含糖酸化鉄群(n=119)に 2:1 で無作為に割り付けされ,FDI は体重 50kg 以上の患者には 1 日 1 回 1000mg での投与が行われた7)8)。 投与開始 12 週後までのヘモグロビン最大変化量は,FDI 群 4.33 ± 0.05g/dL,含糖酸化鉄群 4.27± 0.08g/dL となり,FDI の含糖酸化鉄に対する非劣性が証明されている。 本試験における血清フェリチン値は,FDI 群では投与開始 1 週後に最大(402.10 ±207.99ng/mL),含糖酸化鉄群では投与開始 4 週後に最大(131.57 ± 77.27ng/mL)となった。 FDI 群は,FCM と同様,投与早期に血清フェリチン値が基準範囲を超えていたが,特に有害と思われる事象の発現はなく,その後低減し投与開始 4 週後には 182.02ng/mL となっているため,安全性には問題ないと判断されている。 副作用の発現率は FDI 群で 46.8%(111/237 例)であり,主なものとして発熱 8.4%,蕁麻疹 8.0%,低リン血症 5.9% などが認められた。 低リン血症の発現頻度は,含糖酸化鉄群の 55.5% に比較して大幅に低くなっていることは特筆すべき点と考えられる。 また,18 歳以上の消化管障害に伴う日本人鉄欠乏性貧血患者 40 例(ヘモグロビン値 11.0g/dL未満)を対象とした open-label 試験も実施されており,bolus 静注と点滴静注の 2 群に 3:1 で無作為に割り付け,患者ごとの総投与鉄量に達するまで FDI が投与された9)。 Bolus 静注群では 1 日 1 回 500mg までの投与だが,点滴静注では体重50kg 以上の患者には 1 日 1 回 1000mg での投与も行われている。 ベースラインから投与開始 12週後までのヘモグロビン最大変化量は bolus 静注群 4.27 ± 1.18g/dL,点滴静注群 4.49 ± 2.52g/dLとなり,両群および全体においてヘモグロビンの有意な上昇が認められている。 本試験では,血清フェリチン値は bolus 静注群では投与開始 2 週後に最大(521.79 ± 407.52ng/mL),点滴静注群では投与開始 1 週後に最大(517.70 ± 274.56ng/ mL)となっているが,いずれも 5 〜 6 週後以降に基準範囲まで低減している。 |